息子は生まれた頃は激しく泣いて、抱っこしても散歩しても泣き止まず、近所から夜中に「うるさい」と怒号を聞くほどでした。泣き方がまるで恐怖の真っ只中にあるかのような泣き方でした。「泣き止まない子」というのが息子に対して抱いた最初の感想です。寝ている時や機嫌の良い時は本当に可愛かったです。

その後は6ヶ月検診の時に引っかかり、念の為、地元の発達支援センターで見てもらうことになりましたが、発達支援センターは予約は1ヶ月以上待ち。2回診てもらい、この時は特に異常が見られない、と言われ返されました。里帰りしていたので、私の母は「この子は絶対におかしい、アスペルガーだ」と疑ってききませんでした。
NHKの「すくすく子育て」を見ながら産休を過ごしていて、健康な発達の子どもの育て方を見て「いつか彼もこんなふうに成長するのだろうか。」と少し疑問に思っていました。ちなみに当時は療育について知識などありませんでした。
その後今も住んでいる神奈川県に引越したので、引越し先の発達支援センターにお世話になることになりました。
そこに在籍するドクターに「アスペルガー症候群」と診断されました。当時からすでにない診断名ですが、ASDですね。こちらでエビリファイを処方されてずっと飲んでいました。
薬への知識がなく、エビリファイについて否定的なセカンドオピニオンが多かったこと。効果が目に見えてあるかわからなかったこと。youtubeなどSNSを見ていなかったので、実際に薬を飲んでいる人を見たことがなくて、手探り状態でした。精神疾患の薬はなんとなく悪い影響があるのではないかと怖かったです。
欧米などの海外ではADHDや自閉症についてドラマや映画に出てくることもしばしばなので、エビリファイについては『ぼくと魔法の言葉たち』で見たのが初めてでした。息子とはタイプが異なる自閉症という障害を持った主人公でしたが、障害があっても可能性があると、希望をもらえた映画でした。
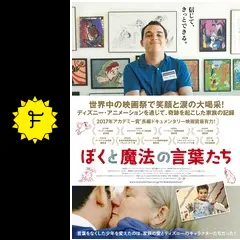

困ったのは保育園の年中から年長期
保育園にお迎えに行くと、担任の先生から、毎回ではないものの、今日は公園から飛び出したとか、癇癪を起こして個室でクールダウンしたとか、聞くようになっていきました。
年長になってからは、お迎えに行くと毎日のように園長先生から呼び止められました。「この子を預かることがどんなに大変か、増配(保育の補助員を増やしてもらう)してもらっても手が足りず、息子1人のためだけに1人保育士が必要な状態。とても人手が足りないので、私(園長)が子どもを職員室で預かって見ている始末だ」と。
暴れるたら手に負えなくなる。目を離せない。たまたま保育士が目を離した隙に他の子が、息子に対してではなく、女の子数名が息子のこだわりのものの配置を変えただけで腹を立て、彼女らに向かって鉛筆を振りかざし首に怪我をさせてしまったこともありました。
迎えに行くとほぼ毎回、苦情を聞き、私は心身疲労が溜まっていました。シングルマザーで実家住みで実母とも関係が悪く、仕事を休むわけにもいかない。八方塞がりで保育園のそばにある踏切に飛び込みたいと何度も思いました。
今振り返ってみると自分でも手に負えない子どもを預かってくれた保育園には感謝しています。
療育について
3歳の時に今の居住地に引越してすぐから発達支援センター通いが始まっていました。
まず処方のために月1で通います。粗大運動・微細運動の苦手さから、作業療法士のOTも月1で通っていました。
前述した保育園でのトラブルが頻発するようになって、緊急性を感じたため、民間の療育に助けを求めに行きました。ネットで調べて、そこだと待機期間もなく、すぐに療育をしてくれるとのことでした。即効性を期待して、ひとまず1回1時間1万円以上する先生と一対一のクラスに数回通わせました。少し遠かったのとやはり経済的に継続することが難しく、こちらは数回だけ通いました。
補助金支援のある児童発達支援というシステムがあるので、週に3回療育することになります。ABA療育と週末は他の療育に2か所、合計3か所に通いました。
その頃から療育の情報は少しずつ増えていましたが、それぞれの事業所の口コミなどもなく、療育センターでの評判を聞きながら選定しました。その後、国の補助金事業のため、新規参入する事業者が一気に増えていきました。新規参入で療育の内容にばらつきが多く、小学校入学後の選定にも苦労します。
療育センターのOTも自発も効果が目に見えてわからず、意味があるのか迷いながらも他にできることが思い当たらず闇雲に通っていました。心理検査をすると、やはり発達に遅れがあるのは明らかだったのと自発の先生からも、小学校は支援級を勧められました。
近くにモンテッソーリ教育をしてくれる保育園などがあれば保育園内で成長させることもできたかもと思いますが、思うように近所にモンテッソーリ教育を行うところはありませんでした。
入学にあたって。支援級という選択
支援級を本格的に検討し始めていました。支援級に入るためには指定された地域の相談室に相談に行く必要があります。息子を連れて息子本人の様子の観察と、親のヒアリングです。2回ほど行きました。この結果は「息子さんは支援級に入る必要がない」というものでした。本人にはスイッチの入るタイミングがあり、 スイッチの入っていない状況でみるとほとんど問題のない、むしろ少し賢いところも垣間見えるようなところがありました。最終的には親が判断できるとのことでしたので、後ろ髪引かれる思いで支援級を選択します。
越境入学した話
それと学区の公立小学校は住んでいるところより少し離れたところにありました。支援級は親の送迎が必須です。学区の小学校は離れていて、生徒数の多い、マンモス校。また、地域性も少し異なっていました。
息子に大人数は耐えられるのか、校舎の古さに清潔さにこだわりのある息子は耐えられるか!?私が送迎し切れるか!?と不安が重なり、近所に住む同じ保育園の子供たちは越境するので、我が家も越境させることにしました。当時の中学受験率は越境させた学校の方が高かったので、比較的おとなしい児童が多いとのことでした。
ここで、私は越境の許可獲得に苦戦します。元々の学区の校長先生との面談はすんなり行きますが、越境先の校長先生がNOを突きつけてきます。自分のプレゼンテーション能力の低さが露呈していたと反省してますが、まあ何度も断られます。越境はできないのが原則なので、即OKとなるわけでもないですが、当時の私は「絶対に越境させる」という意志に燃えていたので、諦めずに何度も面談を申し込みました。越境にあたって相応の明確な理由を添えて結果的にOKになるわけですが、越境すると6年生まで保護者が隣の学区までは必ず送るという縛りがあり、そちらはそちらで苦労することとなりました。
少子化や中学受験、大型マンション建設で生徒数が激動しているので、数年前までマンモス校だった中学校がひと学年2クラス少人数の学校に様変わりしていたり、生徒数の少なかった中学がいつの間にかひと学年7クラス40人学級だったり、日々状況は変化しているので、情報収集は常にした方が良いと実感しました。
終わりに
子育ての苦労話は別途どこかでお話しできればと思いますが、グレーゾーンの子供が公立小学校に入学するまでのお話をさせていただきました。
息子は今年度から中学生です。なので今回お話しした内容は12年前〜6年前の話なので、今とはだいぶ異なるものも少なくないと思います。自分も不安定さがあり、真摯に子どもと向き合えていなかったと思います。自分に余裕があればもう少し息子に対して良い対応ができていたのではないかと後悔することも山のようにあります。この記事がどなたかの励みになれば嬉しいです。


コメント